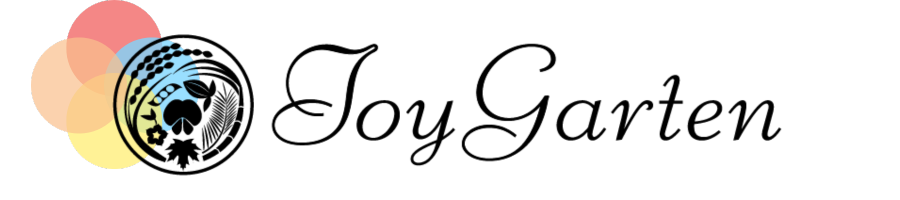沖縄に行ってきました。
海の青さと空の広さに包まれて、自然と、深呼吸が増える日々でした。

もちろん、美味しい沖縄料理も堪能しましたよ〜^^
そんな沖縄で気になったのが、「海に囲まれてるのに、なんで魚より豚肉料理が多いの?」ってこと。
実はこれ、薬膳的に見ても理由があるんです!
かつての沖縄は、男女ともに平均寿命が日本一だったのにも頷けました。
豚肉は、潤いを与えながら元気も補ってくれる
沖縄のような亜熱帯で湿気の多い地域では、体の中に“湿”が溜まりやすく、同時に強い日差しや発汗で“乾き”も起こりやすいんです。
そんなときに大事なのが、潤しながらも、胃腸に負担をかけない食材。
実際に、牛や羊よりも重くなく、消化にやさしいのが嬉しいところ^^
魚ももちろん登場するけど…
沖縄の海では、グルクン・ミーバイ・イラブチャーなどの地魚がたくさん獲れます。
これらの魚も、体を冷まして潤す作用があり、夏にはぴったりの食材。
ただし、魚は体を冷やしやすい一面も。湿度が高くて胃腸が弱ってる時期には、食べすぎると体内に湿をためるリスクも。
だからこそ、魚と豚肉をうまくバランスさせる沖縄の食文化は理にかなってるんです。
昔は「豚=ごちそう」、魚は日常だった!
こうなると、「沖縄って昔から豚肉文化だったの?」と気になる方もいるかもしれません。
実は、昔の沖縄では、豚は特別なごちそう。日常的に食べていたのは魚だったんです。
沖縄は海に囲まれ、グルクンやミーバイ、イカなど、魚介類が豊富にとれる環境。昔の人々にとって魚は、塩漬けや干物などにもして日常のたんぱく源として活躍していました。
一方で、豚肉はというと…
中国との交易を通じて琉球王府に伝わり、当初は王族や士族の“ハレの日の料理”として扱われていた存在。一般庶民が豚肉を食べるのは、法事や祝いごとなど、本当に特別なときだけだったんです。
だからこそ、「豚は鳴き声以外すべて食べる」という言葉が生まれたんですね。
「大切な命を、余すことなくありがたくいただく。」
その精神は今も、沖縄の食文化に根づいています。

戦後の変化で、豚が“日常の味”に!
戦後になると、アメリカ軍の支援や農業政策の変化により、豚の飼育が一般家庭にも広がり、流通も整備されていきました。
そして冷蔵技術の普及とともに、豚肉はより身近な食材へ。
現在のような「豚が主役の沖縄料理」が一般化したのは、比較的最近のことなんです。
薬味や野菜との絶妙な組み合わせ!
豚肉単体で食べるわけじゃなくて、沖縄料理にはよもぎ、島らっきょう、生姜、青パパイヤなどの薬味や野菜がセットで登場。
これらはみんな、体を温め、気を巡らせ、湿を追い出す働きがある薬膳食材!
美味しいだけじゃなく、体を整えてくれる組み合わせになっているのが、沖縄料理のすごいところです。
黒糖の存在も見逃せない!
沖縄料理に欠かせないのが、黒糖。
薬膳では「甘・温」で、気を補い、血を巡らせる食材とされています。
しかも、カルシウムやカリウムなどのミネラルも豊富。
汗をかきやすい沖縄では、黒糖がミネラル補給やエネルギーチャージにぴったりの存在なんです。
ラフテーや煮物、甘味、飲み物にも登場する黒糖は、「濃くて甘い」のに、体をじんわり元気にしてくれる甘味料なんですね。
暑い土地こそ、内臓の冷えに注意!
ちなみに、沖縄のような亜熱帯で暑い土地にいると、「内臓まで暑そう」と思うかもしれませんが、実は逆!
- 暑いからこそ、冷たい飲み物やフルーツをとりがち
- 冷房と外気の温度差で、お腹まわりが冷えやすい
- 湿気が多いと、体内を温めるエネルギーを作る胃腸の働きが弱くなりやすい
暑い環境だからこそ、内臓は冷えやすくなるんです。
暑いからといって体を冷やしすぎず、巡らせながら整える。
本州で生活している私たちも、実は、夏ほど内臓の冷え対策を意識した方が良いんです。
海の幸、豚文化、薬味や島野菜の組み合わせ、そして黒糖。
沖縄の食文化って、まさに「食べる養生」。
暑さに負けない体をつくる知恵が、日々のごはんに詰まっています。
夏バテ、冷え、胃腸疲れ…。
そんなときこそ、沖縄ごはんからヒントをもらって、体を内側から整えていきましょう!