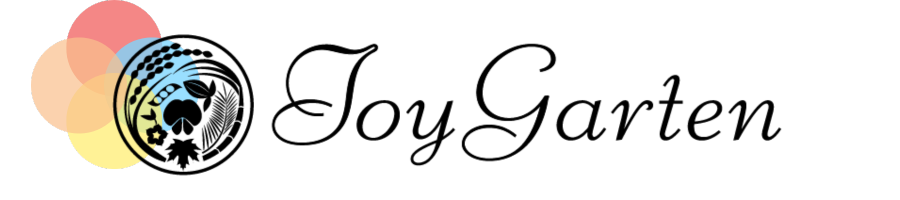朝すっきり起きられない、午後になるとだるくなる、夜になると気持ちが落ち着かない……。
もしかしたらそれ、「体の時間割=子午流注(しごるちゅう)」のリズムとズレているのかも?
中医学には、1日24時間を12の時間帯に分けて、内臓が最も活発になる時間帯を示す「子午流注」という考え方があります。
このリズムに合わせた生活を意識するだけで、体と心のめぐりがスムーズに整ってくるんです!
子午流注(しごるちゅう)とは?
体の「時間割」に合わせて、自分を整える暮らし方。
子午流注は、古代中国医学の知恵。
1日を2時間ずつ12のブロックに分けて、それぞれの時間に最も働く臓腑(内臓器官)を示しています。
このリズムに合わせて、睡眠、食事、休憩、アクティビティのタイミングを意識すると、自然治癒力や免疫力、代謝、心の安定にもつながるとされています。

子午流注の時間割とおすすめの過ごし方
23:00〜1:00(子の刻)— 胆の時間
この時間帯は「胆(たん)」が一番元気に働く時間。胆は消化を助ける胆汁を出すだけじゃなく、実は“決断力”や“やる気”にも関係しています。だから、夜ふかししてると胆がしっかり休めず、次の日のやる気が出にくくなっちゃうかも…。
1:00〜3:00(丑の刻)— 肝の時間
「肝(かん)」は、血を貯めたり、体のデトックスをしたり、気分を安定させるお仕事をしてくれています。この時間にしっかり眠っていると、肝がのびのび働けるので、次の日の肌ツヤや気分の安定にもつながるんですよ。
3:00〜5:00(寅の刻)— 肺の時間
「肺(はい)」が頑張っているのがこの時間。呼吸を通して新しい空気(=気)を取り込み、全身に元気を送る大事な役割をしています。朝方に咳き込む、目が覚めやすいという人は、肺のバランスがちょっと崩れているサインかもしれません。
5:00〜7:00(卯の刻)— 大腸の時間
朝いちばんに働き出すのが「大腸(だいちょう)」。体にたまった不要なものをスッキリ出してデトックスしてくれる時間です。
お腹も心も軽やかに一日をスタートさせましょう^^
7:00〜9:00(辰の刻)— 胃の時間
胃が元気になるのはこの時間帯。つまり「朝ごはんのゴールデンタイム」です!
朝にしっかり温かいごはんを食べておくと、一日のエネルギーがしっかりチャージされて、冷えや疲れにくい体になります。朝食を抜いてしまうと、胃の働きがダウンして、だるさや集中力の低下につながることも…。
9:00〜11:00(巳の刻)— 脾の時間
「脾(ひ)」は、食べたものをエネルギーや血に変えてくれる大切な臓器。
集中力も高まりやすい時間帯なので、頭を使う作業や勉強もスムーズに進みやすいですよ。
11:00〜13:00(午の刻)— 心の時間
「心(しん)」は、血を巡らせて心を落ち着かせるはたらきをしてくれています。この時間帯は感情がちょっと不安定になりやすくもあります。
午後も元気に過ごせるように、ちょっとだけ“自分をいたわる時間”にしてみましょう。
13:00〜15:00(未の刻)— 小腸の時間
小腸は、食べたものから必要な栄養を選び取って、体に届ける働きをしています。
おやつを食べるなら、甘さ控えめで消化の良いものを。緑豆ゼリーや黒ごま団子など、巡りをサポートするスイーツがぴったりです。午後からの活動に向けて、無理せず体を整えてあげましょう。
15:00〜17:00(申の刻)— 膀胱の時間
この時間は「膀胱(ぼうこう)」ががんばってくれる時間。体にたまった余分な水分や老廃物を外に出す準備をしています。
むくみが気になる人は、はとむぎ茶やとうもろこしのひげ茶など、利尿作用のある飲み物もおすすめ。おやつタイムにも、体を温めてくれる黒糖や生姜を使ったスイーツを選ぶと、巡りがさらにスムーズになりますよ。
17:00〜19:00(酉の刻)— 腎の時間
「腎(じん)」は、エネルギーの貯蔵庫のような存在。体力や免疫力、老化予防にも深く関わっています。この時間は、がんばった体をしっかり回復させるための大事な時間。
19:00〜21:00(戌の刻)— 心包の時間
「心包(しんぽう)」は、心を守ってくれる存在。夜のこの時間帯は、副交感神経が優位になって、心と体をリラックスモードに導いてくれるタイミングです。
21:00〜23:00(亥の刻)— 三焦の時間
「三焦(さんしょう)」は、ちょっと不思議な存在で、気や水の通り道を整える“つなぎ役”のような働きをしています。この時間帯は、1日がんばった体をゆっくり整えて、深い眠りへの準備をするのにぴったり。
おすすめ薬膳は、陳皮や桂皮、甘草などを使った体を温めるお茶。静かな夜時間を楽しみながら、明日に向けて心と体をリセットしていきましょう。
子午流注の時間割とおすすめの過ごし方 一覧
| 時間帯 | 臓腑 | 働き | おすすめの過ごし方 |
|---|---|---|---|
| 23:00〜1:00 | 胆 | 回復・解毒 | 深く眠る。夜更かしNG。 |
| 1:00〜3:00 | 肝 | 血の貯蔵・代謝 | 肝を休める時間。足元を温かく。 |
| 3:00〜5:00 | 肺 | 免疫・呼吸 | 朝の空気を意識。乾燥対策も◎。 |
| 5:00〜7:00 | 大腸 | 排泄 | 白湯や温かいスープで排泄を促す。 |
| 7:00〜9:00 | 胃 | 消化 | 朝食のゴールデンタイム。温食が基本。 |
| 9:00〜11:00 | 脾 | 栄養運搬 | 軽めのおやつやお茶で集中力UP。 |
| 11:00〜13:00 | 心 | 精神安定 | リラックス重視。深呼吸を。 |
| 13:00〜15:00 | 小腸 | 栄養吸収 | 昼寝や軽運動が効果的。 |
| 15:00〜17:00 | 膀胱 | 浄化・排出 | 水分補給を意識。薬膳おやつも◎。 |
| 17:00〜19:00 | 腎 | 生命力 | 無理せず体力温存タイム。 |
| 19:00〜21:00 | 心包 | 精神調整 | お風呂・アロマで副交感神経優位に。 |
| 21:00〜23:00 | 三焦 | 気・水分代謝 | 静かな夜時間。心を鎮めて。 |
中医学って「難しそう」と思われがちですが、実はちょっとした工夫で毎日の生活に取り入れられる身近な知恵。
最初から全部の時間を意識するのは難しいかもしれませんが、まずは1日1つの時間帯から、自然のリズムに合わせた生活を心がけてみてはいかがでしょうか?
1ヶ月後には、1日をもっと心地よく過ごせるようになっていますよ^^