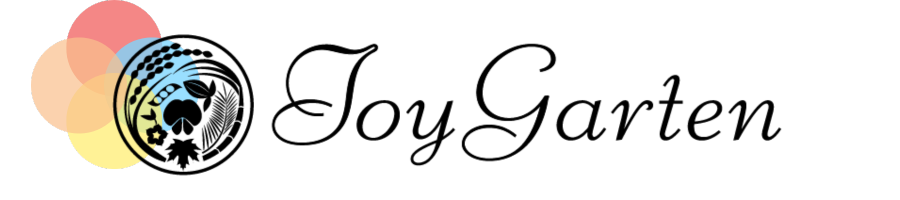秋が深まり、冬の気配を感じ始める11月。
空気がさらに乾燥し、朝晩の冷え込みもぐっと厳しくなってきます。
この時期は、薬膳の考えでは「冬の準備期間」。
エネルギーの貯蔵庫といわれる「腎(じん)」をいたわりながら、体を温めて免疫力を高めることがポイントです。
目次
11月に起こりやすい不調
- 朝、体が冷えて起きづらい
- トイレが近くなる、冷えによる不調
- 疲れがとれにくい、だるさが続く
- 風邪をひきやすい、のどが乾燥しやすい
寒さと乾燥が進むこの時期は、外気の影響を受けやすくなります。体の内側からじんわり温め、気血やうるおいを満たすケアが必要です。
なぜ11月に「腎と免疫の弱り」が起きやすいの?
冷えが強まり腎がダメージを受けやすい
11月は冬の入り口。外気の冷え込みが本格化し、内臓も深部から冷えてきます。
特に影響を受けやすいのが、体の根本を支える「腎(じん)」です。
「腎」は冷えに弱く、またエネルギーの源でもあるため、気温が下がると腎が疲れやすくなり、体力や免疫力が落ちやすくなります。
年末に向けて忙しく、心身の疲れが蓄積される
仕事や学校のイベントごとが増えてくることで睡眠不足・食生活の乱れ・過労が腎に追い打ちをかけ、不調が表面化しやすい時期でもあります。
省エネモードに入る体に対応できず不調が出やすい
自然に備えるモードでも、準備不足だとむくみやだるさ、風邪などの不調が顕著になります。
また、秋からの乾燥や冷えのダメージがたまってきて、冬に備えるだけのエネルギー(気・血・陰陽)が足りなくなる人が多くなります。
「腎」をいたわる暮らしと食事
薬膳でいう「腎」は、生命力や成長、老化、ホルモン、免疫など、さまざまな土台を支えるエネルギーの源です。
暖かくして「腎」を守る
- 首・腰・足首を冷やさない工夫を(マフラー、レッグウォーマーなど)
- お風呂は湯船にゆっくり浸かって、体の芯から温めて
- 夜ふかしを控え、しっかり眠ることも腎を養う養生の一つ
食事で「腎」をサポート
- 黒い食材(黒豆・黒ごま・黒きくらげなど)を取り入れる
- 温かいスープや鍋料理で、気血の巡りをサポート
- 適度な塩味(自然塩)で腎の働きを助ける
11月におすすめの食材と理由
この季節は「温め」「補腎(ほじん)」「うるおい」の3つのキーワードがポイントです。
腎を補う食材(体の土台を整える)
- 黒豆・黒ごま・黒きくらげ:腎を養い、乾燥にも対応
- くるみ・松の実:冷えや疲れに。うるおいもチャージ
- えび・山芋:体を温めながら元気をサポート
体を温める食材(冷え・だるさ対策)
- しょうが・ねぎ・にんにく:寒さで縮こまりがちな体に
- 羊肉・鶏肉・味噌:体を芯から温め、パワーアップ
- シナモン・八角などのスパイス:寒い日におすすめ
うるおいを守る食材(乾燥・風邪予防)
- れんこん・梨・白きくらげ:のど・肌の乾燥対策に
- 豆乳・卵・なつめ:内側からのうるおいをサポート
まとめ:11月は冬に備える月
11月は、冬本番に向けて体をととのえる大切な季節です。
薬膳の視点では「腎を養い、温め、うるおす」ことが健康のカギ。
体の声をよく聞いて、やさしく整えることで、寒さにも乾燥にも負けない体を育てていきましょう。
あたたかいスープや、黒い食材を使ったおやつなどで、心も体もほっとする毎日を過ごしてみてくださいね^^
あわせて読みたい


【10月】秋が深まる季節。「乾燥」と「冷え」から体を守る薬膳ケア
秋も本格的になり、空気がぐっと乾燥しはじめる10月。 肌やのどの乾きが気になったり、朝晩の冷え込みで体調を崩しやすくなったりする時期です。 薬膳では、10月は「肺...
あわせて読みたい


【12月】1年の疲れを癒し、体の芯から温める薬膳ケア
寒さが一段と深まる12月。イベントや年末の忙しさで、心も体もつかれがたまりやすい時期です。 薬膳では、12月は「腎(じん)」をしっかり養う季節と考えられています。...