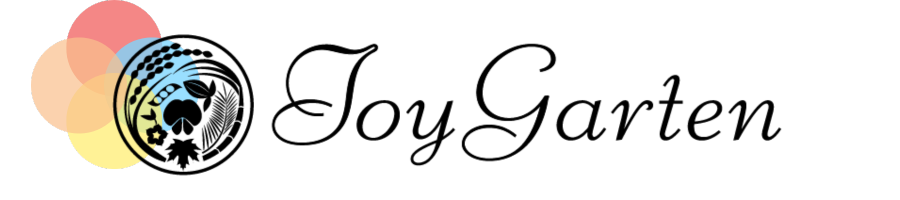「一日一個で医者いらず」と言われるほど、栄養素たっぷりのりんご。
薬膳では脾を補い、胃腸を整える作用があるとされ、消化不良や食欲不振に役立ちます。また、潤いを与えて肺を助け、咳やのどの乾燥にもよいとされます。
皮ごと食べるとポリフェノールや食物繊維がしっかり摂れるのも魅力。秋から冬にかけて体を優しく支えてくれる果実です。
こんな人におすすめ
- 疲れやすく、胃腸が弱い
- 便秘やお腹の張りが気になる
- 乾燥による咳やのどの不快感がある
- 美容やアンチエイジングを意識したい
こんな人は注意
- 冷えやすく、水分代謝が弱い(食べすぎ注意)
- 糖質制限中(果糖が多いため)
目次
主な働き
スクロールできます
| 薬膳的な効能 | 詳細 |
|---|---|
| 健脾(けんぴ) | 胃腸を整えて消化を助ける |
| 潤肺(じゅんぱい) | 肺を潤し、咳や乾燥をやわらげる |
| 生津止渇(せいしんしかつ) | 口の渇きを癒す |
| 通便(つうべん) | 腸を整え、便通を改善する |
| 潤肺(じゅんぱい) | 肺の乾燥を改善する |
| 益胃(えきい) | 胃の働きを助け、消化吸収機能や栄養補給を促す |
帰経
脾・胃・肺に作用し、消化を助けて体を潤す。
薬効データ(性味・五味)
- 性質:平性(体を温めも冷やしもしない)
- 五味:甘味・酸味(滋養・収斂)
食材データ
- 旬:秋〜冬(9月〜12月が最盛期)
- 選び方:表面にツヤがあり、色が鮮やかでムラが少なく、皮にシワがないもの。手に持つと重みを感じるのは果汁が多い証拠。
- おすすめの季節:秋〜春
空気が乾燥し始める時期にぴったり。りんごは「潤肺」「生津」の作用があり、のどや肺を潤して乾燥対策に◎
また、ビタミンCやポリフェノールを含み、免疫力のサポートや抗酸化に役立ちます。温かいコンポートや焼きりんごにすると、体も冷やしにくくなります。
また、気が乱れやすく、ストレスから胃腸に不調が出やすい春にもおすすめです。
栄養学的な特徴
- 食物繊維(ペクチン):腸内環境を整え、便通を助ける
- カリウム:余分な塩分を排出し、むくみを改善
- ポリフェノール(プロシアニジンなど):抗酸化・美肌作用
- ビタミンC:免疫力をサポート
食べ合わせ
相性の良い食べ合わせ
- はちみつ:潤い作用を高め、咳止めに◎
- シナモン:冷えを防ぎ、香りで消化を促す
- ヨーグルト:整腸作用を強化、美肌に
- くるみ:潤いと補腎作用をプラス
- キャベツ:胃もたれや消化不良に
- 人参:発熱時の栄養補給に
注意したい食べ合わせ
- 冷たい飲み物:体を冷やしやすい
- 砂糖の多いスイーツ:糖質過多になりやすい
製菓材料としてのりんご
りんごの主な特性
- 甘味と酸味のバランス:品種によって幅があり、菓子の仕上がりを大きく左右する
- 加熱による変化:生食ではシャキッとした食感だが、加熱するとやわらかくなり、甘味が増して香りが引き立つ
- 水分量が多い:加熱すると果汁が出るため、生地とのバランスや水分調整が必要
お菓子に使うときのポイント
品種選び
甘酸っぱさを生かしたいなら「紅玉」や「ジョナゴールド」。
甘みをしっかり出したいなら「ふじ」や「シナノスイート」。
下処理の工夫
変色を防ぐため、レモン果汁をまぶします。煮る場合は砂糖を少し加えてコンポートにすると、風味と保存性がアップします。
加熱調理の相性
- パイやタルト → バターとの相性が抜群で、香ばしさとジューシーさを両立
- ケーキやマフィン → 角切りやすりおろしで生地に混ぜ込み、しっとり感をプラス
- 焼きりんご → シナモンやはちみつ、ナッツと組み合わせると薬膳的にも◎
食感を生かすか消すか
シャキッと感を残したいときは短時間加熱、とろける口当たりにしたいときはじっくり煮込みます。
保存とアレンジ
ジャムやキャラメリゼにすると、酸味と甘味のバランスが長期間楽しめる。煮りんごやピューレにして冷凍すれば、いつでも使えて便利。