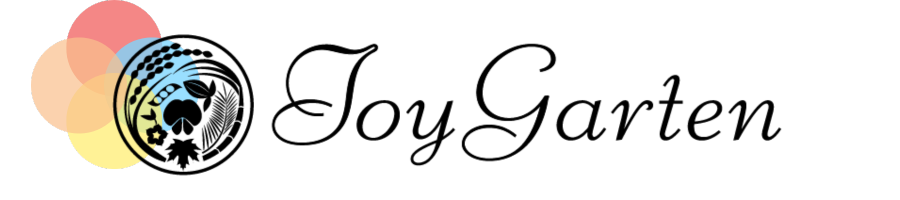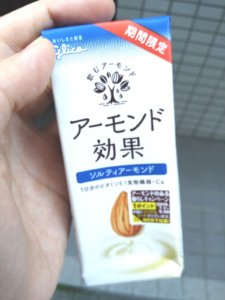焼きたてのバターの香り、しっとりとほどける食感…。
パウンドケーキには、どこか「ほっとする」力があります。
実はこの素朴なお菓子、長い歴史をたどって、世界中で愛され続けてきたことをご存じでしょうか?
今回は、そんなパウンドケーキの起源と、作るときのポイントをご紹介します。
パウンドケーキの起源と歴史
パウンドケーキのルーツは、18世紀のイギリスにさかのぼると言われています。
その名の通り、小麦粉・バター・砂糖・卵をそれぞれ1ポンドずつ(約450g)使って作るという、非常にシンプルかつ実用的な配合が特徴です。
当時はまだ、一般家庭に秤(はかり)が普及していなかったため、同じ重さで揃えるレシピはとても便利で、誰にでも再現しやすいものでした。
この「等量で混ぜる」スタイルが、多くの人々に受け入れられ、パウンドケーキは家庭の定番スイーツとして親しまれるようになったのです。
その後、ヨーロッパ各地やアメリカに渡り、バターの代わりにサワークリームやヨーグルトを使ったもの、フルーツやスパイスを加えたものなど、各地で独自のアレンジが加えられていきました。
特にフランスでは「カトル・カール(quatre quarts)」という名前で知られ、フランス菓子の一つとして根づいています。
そして現代では、小麦粉を米粉やアーモンドパウダーに置き換えたり、バターではなく植物油脂を使ったりと、素材や食感の自由度が広がり、健康志向にもフィットするスイーツとして進化し続けています。
パウンドケーキ作りのポイントは「乳化」と「温度管理」
パウンドケーキをしっとり、ふんわりと焼き上げるため重要なのが、「乳化」と「温度管理」です。
難しそうに感じますが、ほんの少しの気配りで、いつものパウンドケーキがぐんと格上げされます。
卵と油脂をなめらかに混ぜる“乳化”
乳化とは、本来混ざり合わない油と水(卵)を、なめらかに一体化させる工程のこと。
この工程がうまくいくことで、生地が均一に膨らみ、口当たりのよい仕上がりになります。
乳化のポイントは3つです。
材料はすべて常温に戻す
冷たいままだと、バターや油脂が固まり、分離の原因になります。
卵は一気に加えず、数回に分けて少しずつ混ぜる
一度に加えると、水分と油脂がなじむ前に分離してしまうため注意が必要です。
しっかり混ぜ合わせる
ハンドミキサーでツヤが出て、もったりと白っぽくなるまで混ぜるのが理想です。ミキサーがない場合は、ホイッパーで卵を加えるたびにしっかりと混ぜて乳化させていきましょう。
この乳化がうまくできると、生地がふんわりと空気を含み、焼き上がりにパサつかず、しっとり感が続くケーキになります。
美味しさを左右する温度管理
材料の温度だけでなく、焼成温度や焼き上がり後の冷まし方も、食感と風味に大きな影響を与えます。
オーブンはしっかり予熱を
設定温度に達する前に焼き始めると、膨らみが悪くなったり、焼きムラの原因になります。
温度は10℃違うだけで仕上がりがまったく変わるため、ご自宅のオーブンの癖に合わせて温度調整することも大切です。
焼き上がったら、すぐにラップで包む
温かいうちにラップで包むことで、水分が閉じ込められ、時間が経ってもしっとり感が保たれます。
冷蔵庫で一晩寝かせるのがおすすめ
焼きたてよりも、時間が経ってからの方が、味がなじみ、香りも落ち着いて全体がまとまりやすくなります。
薬膳パウンドケーキ
長い歴史の中で、人々の暮らしに寄り添ってきたパウンドケーキ。
そこに、薬膳の考え方「からだにやさしく、季節に寄り添う。」というエッセンスを重ねることで、もっと自分や大切な人をいたわるお菓子に育てていくことができます。