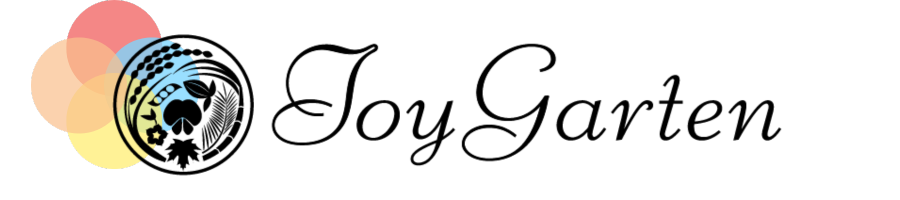煮物やカレーを冷蔵庫に入れておくと、表面に白っぽい脂が固まっていることがありますよね。
「あぁ、冷えて固まったのね」と思うその脂は、動物の種類によって固まり方に違いがあるってご存じでしたか?
固まり方の違いは、その動物の「体温」と「脂のとける温度(=融点)」の関係にあるんです。
この記事では、「動物の体温」と「脂肪の融点」という視点から、お肉の消化のしやすさや、わたしたちの体への影響を見てみます。
薬膳や中医学の考え方も交えながら、体質や季節に合ったお肉との付き合い方をご紹介していきますね。
そもそも「融点」ってなに?
「融点(ゆうてん)」とは、脂が固体から液体に変わる温度のことです。
つまり、「脂がとけはじめる温度」のこと。
冷蔵庫でカチカチだったバターが、トーストにのせた瞬間にスッととけるように、脂も温度が上がるとやわらかくなっていきますよね。
お肉の脂も同じで、それぞれの動物の脂は、ちょうどその動物の体温くらいで溶けやすくできているんです。
体温が高い順に見てみよう 〜動物と脂肪の融点の一覧〜
脂はすぐにエネルギーに変換できる、大切な栄養素。
動物の体の中では、脂は液体に近い状態でないとスムーズに使えません。
基本的には体温よりも脂の融点は低くなっているのですが、例外もあります。
例えば…
- 鶏の体温は約41℃。脂の融点も40℃前後。
- 豚の体温は約39℃。脂の融点もそれに近い温度。
- 【例外】牛の体温は約38℃。脂の融点は少し高め。
体温が高い順に、脂肪の融点と特徴を見てみましょう。
※赤い太文字は例外の動物の脂肪の融点です。
| 動物 | 体温(℃) | 脂肪の融点(℃) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 鶏 | 41.0〜42.0 | 約30〜35 | 低融点の軽い脂肪、消化に良い。脂肪の質がやわらかく、体にスムーズになじむ。 |
| 鴨 | 41.0〜42.0 | 約35〜38 | 鶏より脂が多くコクあり、だが融点は低めで比較的消化しやすい。温補効果もある。 |
| うさぎ | 38.5〜40.5 | 約30〜38 | 低脂肪・高たんぱくで、脂肪は非常に軽い。不飽和脂肪酸が多く消化が良い。 |
| 山羊 | 約39.0〜40.5 | 約44〜50 | 脂肪量は少なめだが、融点はやや高め。全体的にはあっさりしているが温補効果もある。 |
| ラム | 約39.5 | 約40〜50 | 子羊肉であり、脂はやや高融点。比較的軽く、初心者にも食べやすい。温補に適する。 |
| マトン | 約39.5 | 約44〜55 | 成羊肉で、脂肪の融点が高く冷えると固まる。体を温める力が強いが、胃に負担をかけやすい。 |
| 鹿(夏) | 約39.0 | 約30〜40 | 夏は脂肪が少なく、融点も低め。不飽和脂肪酸が多く、あっさりとした味わい。 |
| 鹿(冬) | 約39.0 | 約45〜55 | 冬に備えた脂肪を蓄えるため融点が高くなる。温補力があり、体を芯から温める。 |
| 豚 | 約38.5〜39.5 | 約40〜45 | 潤いを補う脂を含む。やや重たいが、消化力があれば問題なし。痰湿体質には注意。 |
| 牛 | 約38.5 | 約50〜60 | 高融点の脂で冷えると固まる。重厚な肉質で、胃に負担がかかりやすい。温補効果は強め。 |
| 魚 (熱帯性) | 約15〜25 (環境依存) | 約10〜30 | 暖かい海に住む魚で、飽和脂肪酸も含む。脂の融点はやや高めでしっかりとした身質。 |
| 魚 (冷水性) | 約0〜10 (環境依存) | -30〜-5 | 寒冷地の魚で、極端に低融点の脂肪を持つ。非常に吸収がよく、EPAやDHAが豊富。 |
どうしてこんなに差があるの? 〜自然と暮らしの知恵〜
体温よりも脂の融点は低い方が良いはずなのに、そうじゃない動物もいるのはなぜでしょう?
おもしろいことに、動物の住む環境や消化吸収の仕組みによっては、体温より融点が高いほうが都合が良い場合があるんですね〜。
その理由を見てみましょう。
1. 生息環境の違い
牛やマトンのような陸上の恒温動物では、脂が冷えても凍らないうえに活動量も多くはないため、高融点の脂肪を持つことで、保温やエネルギー蓄積に役立てています。
一方、冷たい海に住む魚は、脂が凍ってしまうと動けなくなるため、体温よりはるかに低い融点の脂肪をもっています。
2. 消化吸収の仕組み
4つの胃を持つ反芻動物(牛・羊・山羊など)は、一度飲みこんだ草を、もう一度口に戻してモグモグかみなおす、というちょっと特別な食べ方をしています。
この「モグモグ→ゴックン→またモグモグ」を何度もくり返すことで、草を時間をかけてじっくりと発酵させて、栄養を吸収しやすい形に変えています。
その過程で、飽和脂肪酸(冷えると白く固まりやすい脂)を体内で合成しているため、結果的に高融点の脂を持ちやすいです。
逆に、消化器官が単純な鶏やうさぎは、比較的低融点の脂を持つ傾向があり、これが消化のしやすさにもつながります。
3. 活動量と代謝の違い
活動的な動物(鶏・鴨・鹿など)は、筋肉質で脂肪が少ないため、体内の脂肪をすみやかにエネルギーに変換しなくてはなりません。そのため、脂肪も柔らかく体温以下の温度で溶けやすいものが多いです。
特に野生の鹿は、夏と冬で脂肪の質自体が変化し、環境に合わせて適応しています。
お肉ごとの特徴と効能
焼肉や炒め物、お鍋など、いろんなお肉を使った料理をしていると、「あれ?このお肉は脂が軽い」「このお肉はコクがあるけど、後でちょっと重たく感じる」そんな経験、ありませんか?
それも、脂のとけやすさ=融点が関係しています。
実際、牛肉を使ったすき焼きの残りを冷蔵庫に入れておくと、次の日には脂が白く固まっていた、なんてことありますよね。
ここでは、お肉ごとの特徴やおすすめの体質をご紹介します。
鶏 ― すっとなじむ、あたたかな軽やかさ
鶏は、わたしたちの食卓でもっとも身近なお肉のひとつ。中医学で言えば、「気」を補い、「脾」を整える力があるとされ、消化の負担が少なく、体に優しく寄り添う存在です。
鶏の体温は、動物の中でも特に高く、およそ41〜42℃。それに対して、脂肪の融点(脂が溶けはじめる温度)は30〜35℃ほど。
これは、人間の体温(約36.5℃)でも自然にとろける軽やかな脂です。
だからこそ、鶏肉は、
- 冷えても脂が白く固まりにくく、
- 消化もしやすく、
- 脂が残る感じが少ない。
それはまるで、「受け取ったものを、すっと手放せるような軽やかさ」をもった肉質。疲れているとき、胃腸が弱っているとき、優しく体を支えてくれる食材です。
薬膳的にも、気虚・脾虚・虚弱体質の方にぴったり。温かなスープにして、香り野菜や生姜と合わせると、よりからだに染み渡ります。
鴨 ― じんわり温まる、芯からの巡り
鴨は、同じ鳥類でも鶏とはまた違う個性をもっています。
体温は鶏と同じく41〜42℃と高めですが、脂の融点は少し高く、約35〜38℃前後。
脂肪の量も鶏より多めで、口あたりにコクと深みがあるのが特徴です。
この鴨の脂、実はとても優秀。
人の体温でも十分溶けやすく、それでいてしっかりとした温め力があるのです。
冬の冷えた日には、鴨鍋や鴨南蛮のように「巡りを助ける温性食材」として重宝されてきました。
薬膳の観点では、鴨は「補腎陰・養胃陰」とされ、潤いを補いつつ温めるという貴重なバランスを持ったお肉。
特に、冷えによる血行不良や、虚弱体質で陰陽のバランスを崩しやすい方におすすめです。
「冷えの奥にある疲れ」をじんわりとゆるめ、巡らせてくれる。
そんな、芯から包み込むようなやさしいエネルギーを持ったお肉です。
うさぎ ― 軽やかな滋養、陰を補う透明さ
うさぎのお肉は、日本ではまだ馴染みが薄いかもしれませんが、薬膳の世界では古くから「虚弱体質の回復」「皮膚や粘膜の潤い補い」として用いられてきました。
うさぎの体温は、鶏や鴨よりやや低めで約38.5〜40.5℃。
それに対して脂肪の融点は30〜38℃ほどと、とてもやわらかく溶けやすい性質を持っています。
しかも、うさぎは脂肪の量自体が少なく、お肉の95%以上が赤身の高たんぱく質。
脂の質も不飽和脂肪酸が中心で、からだにすっとなじみやすく、食べたあとの軽さが特徴です。
薬膳では、うさぎ肉は「補中益気・補腎養陰」とされ、疲れたとき・潤いが不足しているとき・風邪の後などの回復期にとても良いとされています。
「元気にしたいけど、重たくしたくない」
そんな想いにぴったり寄り添ってくれる、軽やかで静かな滋養をもったお肉です。
山羊 ― 静かに燃える芯の火
山羊は、牛や羊と同じく「反芻動物(胃が4つある)」の仲間。
体温は39.0〜40.5℃と高めで、脂肪の融点は約44〜50℃とやや高く、体温ではすぐには溶けきらない、しっかりとした脂質をもっています。
この融点の高さは、体の深部を温める「陽」の力を象徴しています。
だからこそ、山羊のお肉は、芯から温める力がとても強いのです。
薬膳では、山羊は「温中補陽・散寒通絡」とされ、
陽虚体質・慢性的な冷え・虚弱からくる痛み(腰・関節など)に用いられます。
ただし、脂肪がやや重たく感じられることもあるため、にんにく・生姜・シナモン・クミンなどの「温性の香り食材」と一緒に調理するのがベスト。
体の奥にある「陽気の火」を、静かに、でも確実に灯してくれるような存在。
そんなイメージを持って、寒い季節や疲労の深いときに取り入れてみてください。
ラム ― やわらかに芯を温める、やさしい温補肉
ラムは生後12ヶ月未満の子羊のお肉で、マトンに比べて脂がやわらかく、香りも控えめ。
体温は約39.5℃、脂肪の融点は約40〜50℃で、やや高めですが、マトンよりは溶けやすい性質を持っています。
薬膳では、ラムは「温補腎陽・温中散寒」に分類され、冷えからくる不調や、体の芯の冷えをやわらかく温めるのに適しています。
特に、女性の冷え症や慢性的なだるさ、寒がりタイプの疲労感におすすめです。
クミンや陳皮、シナモンなどと一緒に調理することで、消化の負担を軽くしながら巡りもサポートできます。
「温めたいけど重すぎたくない」そんな方にぴったりの一品です。
マトン ― しっかりとした力強さ、深部からの温め
マトンは成羊の肉で、脂肪の融点は約44〜55℃と非常に高く、冷えると白く固まるほどの重厚な脂質を持ちます。
体温はラムと同じく約39.5℃ですが、より引き締まり、食べ応えも抜群。
薬膳では「温腎壮陽」の代表格で、体力の消耗が激しい人や、極度の冷え、腰や膝が重だるいような症状に最適とされます。
ただし、消化には負担がかかりやすいため、しっかりと火を通し、生姜や山椒などの発散性スパイスと組み合わせるのが理想です。
「温める力」は肉の中でも随一。
必要なときに、しっかりと頼れる肉です。
鹿(夏) ― 軽やかな野生の力、巡りと回復に
夏の鹿肉は、脂肪が少なく、融点も30〜40℃ほどと比較的低め。不飽和脂肪酸が多く、食後の重さが残りにくいのが特長です。
活動量が多く、野山を駆けるような野生動物らしい、筋肉質で引き締まった赤身肉です。
薬膳では「補腎益精・補血活血」とされ、疲労回復や巡りの改善、貧血気味の方のサポートに向いています。
熱をこもらせにくく、夏場でも取り入れやすい優秀な赤身肉です。
鹿(冬) ― しっかり蓄えた脂のぬくもり
冬の鹿肉は、寒さに備えて脂肪を蓄え、その脂は約45〜55℃と融点が高くなります。
野生の動物が冬を越えるためのエネルギー源とも言える、濃厚で保温力のある脂です。
薬膳的にも「温腎補陽・強筋健骨」とされ、冷えやすい冬、腰や膝の不調、体力の消耗におすすめ。
野生の鹿の持つ生命力を、からだの芯に取り込むような感覚でいただくとよいでしょう。
豚 ― 潤いを届けるやさしさ、ほどよい重さ
豚は体温が約38.5〜39.5℃で、脂肪の融点は約40〜45℃。脂がやや重たく感じられることもありますが、潤いを補う作用があるのが大きな魅力です。
薬膳では「補陰潤燥・滋養強壮」とされ、喉の渇き・乾燥・便秘・皮膚のかさつきといった潤い不足の症状に良いとされています。
ただし、痰湿体質(むくみ・だるさ・脂っこいものが苦手な人)は取りすぎに注意が必要です。
蒸し料理やスープにすることで、脂の重さをやわらげ、より穏やかに吸収されます。
牛 ― 力強さと重たさ、温補の王様
牛の体温は約38.5℃、脂肪の融点は50〜60℃とかなり高く、冷えると白く固まり、消化に時間がかかる脂です。
これは反芻動物特有の代謝の特徴ともいえます。
薬膳では「補気養血・健脾補中」とされ、虚弱・体力低下・冷え・血虚など、根本的なエネルギー不足の補いに向いています。
体力があるときや、寒さに負けそうな時期には、頼もしい味方となりますが、胃腸が弱っているときや、湿がこもりやすいタイプの方は少量から様子を見るとよいでしょう。
中医学・薬膳の視点で考えるお肉の選び方
消化のしやすさと脂の融点の関係
脂肪の融点が人の体温(約36.5℃)に近い、あるいはそれ以下であれば、体内でスムーズに溶け、消化・吸収も良くなります。
高融点の脂(牛・マトン・冬鹿など)は冷えると固まりやすく、胃腸が弱い人には負担になります。
体質別に向いているお肉
| 体質 | おすすめの肉 | 理由 |
|---|---|---|
| 気虚・脾虚 | 鶏・うさぎ・鴨 | 消化しやすく、気を補う作用がある |
| 陽虚(冷え) | 羊・マトン・鹿(冬) | 温補作用があり、芯から体を温める |
| 湿熱 | 魚(冷水性)・うさぎ | 脂が軽く、余分な熱や湿をこもらせない |
| 血虚 | 鶏レバー・豚レバー・鴨 | 血を補う作用があり、鉄分・ビタミンが豊富 |
| 陰虚 | 鴨・うさぎ・豚肉(赤身) | 潤いを補いながら、余分な熱を生まない |
季節による選び方
- 冬:温め力の強い「羊・鹿・鴨・牛」など高融点脂肪の肉が◎
- 夏:軽やかで消化しやすい「鶏・うさぎ・魚」など低融点脂肪の肉が◎
とけにくい脂は、体の中でも固まりやすい?
人間の体温は36.5℃前後。
この体温で溶けにくい脂をたくさんとると、体の中でベタついて残りやすくなる可能性もあるんです。
特に、体が冷えやすい人、胃腸が弱めの人には、融点が高い脂はちょっと重たく感じられることも。
でも、これは「牛肉を食べちゃいけない」という話ではありません。
食材の特徴を知って、食べ方を工夫することが大切なんです。
例えば
- 牛肉は熱を加えてしっかり温かいうちに食べる
- たっぷりの野菜や薬味と一緒にいただく
- 消化を助ける香味野菜(生姜、にんにく、大根など)や香辛料(カルダモン、クミン)を合わせる
こうした工夫で、体への負担を減らすことができます。
「知って選ぶ」が、毎日のごはんをもっと楽しくする
お肉の脂にも、それぞれの個性があります。脂のとけやすさを知ることで、料理の仕上がりや体への優しさがグッと変わります。
- 軽く食べたい日には鶏肉を。
- コクを楽しみたい日は豚肉や牛肉を。
- 食べ合わせや調理法を工夫して、脂とうまく付き合う
そんなふうに食材と仲良くなることで、「なんとなく」だった日々のごはんが、ちょっと特別な養生ごはんに変わるかもしれません。
食の知恵と東洋の知恵を掛け合わせて、「食べること」が心と体を整える時間になりますように。