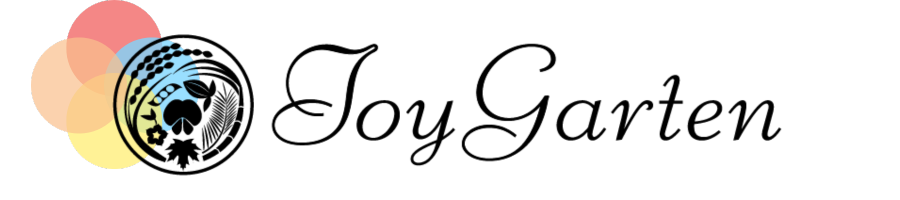アーモンドは、乾燥対策や体力維持、脳の活性化、美肌ケアに役立つ食材。
栄養豊富で日常的に取り入れやすく、季節を問わずおすすめですが、少毒があるため1日10粒程度にしましょう。
- 乾燥しやすい(陰虚)
- 疲れやすい、体力が落ちやすい(気虚)
- 便秘しやすい人
- 美肌・エイジングケアに
- 秋〜冬に体調を崩しやすい人
- 消化力が弱い人(大量摂取に注意)
- ニキビや吹き出物が出やすい
- ナッツアレルギー
アーモンドの効能
主な働き
肺をうるおし、喉の乾燥や空咳を和らげる働きに優れています。また、脾胃を助けながら気血を補い、美容やエネルギー補給にも効果的です。
| 薬膳的な効能 | 詳細 |
|---|---|
| うるお肺止咳(じゅんぱいしがい) | 肺をうるおし咳を鎮める |
| 補血健脾(ほけつけんぴ) | 血を補い、消化を助ける |
| 通便(つうべん) | 便通を促す |
| 安神(あんしん) | 精神を安定させ、心を落ち着かせる |
帰経
肺・大腸・脾・心に作用し、呼吸器の調整、腸や胃腸全体、精神の安定に関わる。
薬効データ(性味・五味)
- 性質:平性(穏やかに体を整える)
- 五味:甘味(ゆるやかに補う)
食材データ(旬・選び方・おすすめの季節)
- 旬:8〜11月頃(効率的な収穫体制や加工技術の発達により、通年手に入れることが可能)
- 選び方:傷がなく、色ツヤがよくて鮮やかなものを選ぶ
- おすすめの季節:秋〜冬(9〜2月)
うるお肺・うるお腸の作用があるアーモンドは、乾燥しやすい秋ののどや肺をうるおすほか、冬には腎や体力を養う補養食材としても役立ちます。
栄養学的な特徴
- ビタミンEが非常に豊富(抗酸化作用)
- 良質な脂質(オレイン酸)を含む
- たんぱく質、食物繊維、カルシウムも多い
- 血糖値コントロールやコレステロール対策にも期待できる
食べ合わせ
「相性が良いからたくさん食べても良い!」「相性が悪いから、絶対食べちゃダメ!」
というわけではなく、その時の食べる人の体質に合わせて調整することがポイントです。
相性の良い食べ合わせ
- はちみつ(うるお肺・のどケア)
- 豆乳(たんぱく質補給・うるおいケア)
- 黒ごま(補血・美肌強化)
- 甘酒(補気・補血サポート)
- なつめ(補血・精神安定)
注意したい食べ合わせ
摂りすぎたり、摂り方によっては消化器系に負担がかかるため注意。
- 脂質の多い食事と組み合わせる
- 冷たいものと一緒に摂りすぎる
製菓材料としてのアーモンド
アーモンドは、コクのある甘みと豊かな香ばしさを持ち、製菓に欠かせない存在です。丸ごとローストしてトッピングに使うほか、スライス、ダイス、パウダーなどに加工して、焼き菓子や生菓子に幅広く応用されています。香り・コク・食感の三拍子が揃った食材です。
アーモンドの主な特性
- 豊富な油脂分がコクとしっとり感をもたらす
- 加熱によって香ばしさがさらに引き立つ
- ナッツ特有の甘みがあり、自然なやさしい味わいに仕上がる
- 食感のアクセントにもなり、トッピングや練り込みにも適している
- グルテンを含まないため、ふんわり感を出すには工夫が必要
アーモンドパウダーについて
アーモンドを細かく粉砕すると、アーモンドパウダー(アーモンドプードル)になります。しっとりとした食感とコクを出してくれるため、製菓においても長年に渡り重宝されています。
マカロンやフィナンシェ、ガレットブルトンヌなど、アーモンドの香りとコクを活かしたスイーツに欠かせません。
アーモンドをお菓子に使うときのポイント
ローストすると香りが引き出される
トッピングや練り込み用のアーモンドは、軽くローストすると香ばしさが引き立ち、風味豊かな仕上がりになります。焦げすぎないよう、160〜170℃程度で香りが立つまで焼くのがコツです。
アーモンドパウダーは早めに使う
アーモンドパウダーは空気に触れると酸化しやすいため、開封後はなるべく早めに使い切るか、密閉して冷蔵保存します。酸化を防ぐことで、鮮度の良いコクを保てます。
水分バランスを考える
アーモンドパウダーを多く使うと油脂分が多くなり、しっとりリッチな仕上がりになりますが、水分量や焼成温度にも注意が必要です。焼きすぎるとパサつきやすくなるため、低温でじっくり火を通すとしっとり感がキープできます。
粉の一部を置き換えてコクをプラス
小麦粉100%のレシピの一部をアーモンドパウダーに置き換えると、グルテン量が減ってふんわり感が増し、香ばしくコクのある味わいに仕上がります(目安は全体の10〜30%程度)。
アーモンドを使ったスイーツ