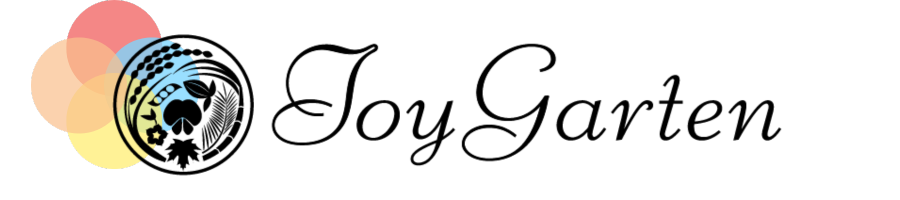小豆の赤い色には「補血」、サポニンには「利水・排毒」作用があるとされます。薬膳では「心」「脾」「腎」に帰経し、むくみ・肌荒れ・疲れやすさなどにおすすめの食材。甘さとの相性も良く、和菓子や薬膳スイーツにも重宝されています。
- むくみやすく体が重い
- 肌荒れや吹き出物が気になる
- 月経トラブルやPMSがある
- 貧血ぎみ
- 目の下にクマができやすい
- 爪がボロボロ
- 冷え性で下痢しやすい
- 胃腸が弱く、豆類でお腹が張りやすい
- 乾燥体質の方(過剰摂取に注意)
主な働き
| 薬膳的な効能 | 詳細 |
|---|---|
| 利水(りすい) | むくみを改善し、余分な水分を排出 |
| 解毒(げどく) | 体内の毒素を排出し、肌荒れ予防 |
| 補血(ほけつ) | 血を補い、貧血や月経トラブルをサポート |
| 消腫(しょうしゅ) | 腫れ・腫れ物を消して体全体のバランスを整える |
帰経
肝・脾・腎に作用し、むくみや疲労をケアしながら、血の巡りと水分代謝を整える。
薬効データ(性味・五味)
- 性質:微寒〜平性(解毒作用があり、涼寄りの平性)
- 五味:甘味・酸味・苦味(補う・解毒)
食材データ(旬・選び方・おすすめの季節)
- 旬:収穫は秋(10月〜11月)だが、乾物として通年手に入りやすい
- 選び方:粒がそろっていて、表面につやがあり、割れや虫食いがないもの
- おすすめの季節:冬〜夏・長夏(湿度が高くなる時期)
小豆は体内の余分な水分を排出する作用があり、湿気によるむくみが気になる季節や、身体がこわばりやすく巡りが滞りがちな冬におすすめです。
ただし、寒がりで冷え性の人が冬に大量に摂ると、体を冷やしてしまう可能性が高いため、体を温める食材と一緒にとるようにしましょう。
栄養学的な特徴
- カリウム:利尿作用でむくみ軽減
- 鉄・葉酸:貧血予防、血を補う
- サポニン:抗酸化・利尿・解毒作用
- 食物繊維:腸内環境の改善に役立つ
食べ合わせ
相性の良い食べ合わせ
- 黒ごま:補血・補腎効果を高める
- もち米:消化しやすく、胃腸を助ける
- はちみつ:うるおいを補い、甘さをやさしく調和
- かぼちゃ:脾胃を補い、エネルギー補給に◎
- 昆布:カリウム豊富で利尿作用の相乗効果
- トマト:瘀血解消の相乗効果で、血流を良くする
注意したい食べ合わせ
- 冷たい飲料や果物:お腹を冷やしやすい
- 油脂が多いスイーツ:消化に負担がかかる
- 他の豆類:豆類を食べすぎると消化に負担がかかる
製菓材料としての小豆
煮るだけで甘味を加えた餡にしやすく、優しい自然の甘さが活かせます。粒感を残すと食感も楽しく、見た目にも温もりが出ます。
主な特性
- 自然な甘みとコクがあり、砂糖控えめでも美味しい
- 煮崩れしにくく、形を活かした盛り付けが可能
- 冷凍保存しやすく、作り置きに便利
お菓子に使うときのポイント
アク抜きはケースバイケース
一度下茹でしてから甘味を加えますが、アク抜きは目的によって使い分けましょう。
- アク抜き無し:小豆の効能が高く仕上がりますが、小豆本来の雑味が残ります。
- アク抜き有り:消化負担を減らし、すっきりとした風味に仕上がります
私はアク抜き無しが好みです^^
食感の調整
潰しすぎず、軽く粒を残すと満足感と食物繊維の働きを活かせます(粒あん)。
こしあんにしたい場合は、漉し器やミキサーでなめらかに調整します。
温冷の使い分け
冬は温かいお汁粉や蒸し菓子にすることで、冷え性の人でも体を冷やさず食べられます。
夏は羊羹・ゼリーやアイスなどで、涼性のスイーツに仕上げても良いでしょう。
甘味の調整
小豆本来の風味を活かすため、はちみつや甜菜糖など、優しい甘味料がよく合います。
また、天然塩を適度に加えることで、味が引き締まります。
あんこの効能
あんことあずきは素材としては同じ「小豆」ですが、薬膳的・調理的に見ると以下の違いがあります。
- あずき(素材)は、より「利水・解毒・補血」の性質が活きる。
- あんこ(加工品)は、加糖されることで「補気・補血」が強調されやすい。
一般的な白砂糖が使われているあんこは、甘味が追加されることで脾胃を補う作用が加わりますが、一方で、湿を生みやすくもなります。
「あずきは薬効中心、あんこは甘味と栄養補助」という役割の違いを意識すると使いやすいでしょう。
他にも、甘味料によってあんこの効能は異なります。
| 甘味料 | 主な効能 | 特徴 |
|---|---|---|
| 白砂糖 | 一時的に気を補うが、湿熱を助長しやすい | 常食すると脾胃に負担、控えめ推奨 |
| てんさい糖 | 補気・温中(体を内側から温める) | 北方産、冷え性の人におすすめ |
| きび糖 | 補中益気・潤肺 | ミネラルを多く含み、優しい甘さ |
| はちみつ | 潤肺・生津・緩急止痛 | 乾燥対策や喉の不快感に◎ |
| 黒糖 | 補血・温中散寒 | 冷え・血虚タイプに特に適している |
| 米麹 | 消化促進・健脾和胃・補気 | 発酵によって消化吸収がスムーズになる |