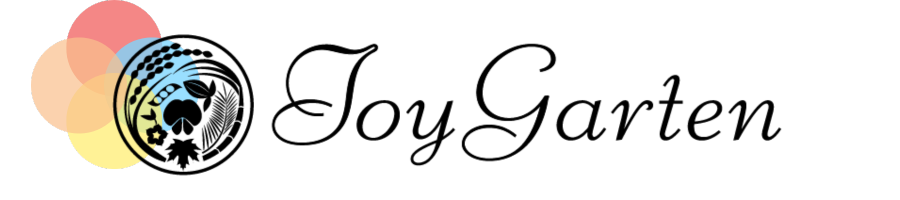6月は梅雨に入り、雨の日や湿度の高い日が続きますよね。
なんとなく体が重かったり、むくみやすかったり、気分もスッキリしない…そんな不調を感じる人が増える季節。
薬膳の考え方では、こうした不調は「湿気」が体にたまることで起こるとされています。
特に、消化を助ける「お腹(脾)」が湿気に弱く、余分な水分や老廃物が体の中にたまってしまいやすいんです。
あわせて読みたい


むくみ・だるさをリセット!【梅雨】を快適に過ごす食養生
梅雨の時期って、心なしか体も心も重だるいような気がしませんか? 中医学では、体に溜まった「余分な水分」が、巡りを滞らせたり、重だるさを引き起こしたりする状態を...
目次
体にたまりやすい「湿気」に注意
湿度が高いこの季節は、体の中にも「湿気」がこもりやすくなります。
その結果、次のような不調が出やすくなります:
- 胃がもたれる、食欲がない
- 体がだるい、やる気が出ない
- 足や顔がむくむ
- 頭が重い・ボーッとする
こういった不調は、「痰湿」と「脾の不調」が原因。体の中の「余分な湿気」を外に出してあげることが大切です。
なぜ6月に「痰湿」と「脾の不調」が起きるの?
梅雨の湿気が体に影響する
空気中の湿度が高くなる6月は、体内にも「湿気=湿邪(しつじゃ)」がたまりやすくなります。
余分な水分がうまく排出できないと、だるさ・むくみ・頭重感などの「痰湿(たんしつ)」の症状が現れやすくなります。
脾(胃腸)が湿気に弱い
薬膳では「脾は湿を嫌う」といわれ、湿度が高いと消化吸収の働きが落ちてしまいます。
そのため、胃のもたれや食欲不振、軟便なども起こりやすくなります。
5月の「気滞」が引き金になることも
5月に気が滞ったまま6月を迎えると、体内の巡りが悪くなり、湿もたまりやすくなります。
このため「気滞」と「痰湿」が組み合わさって、不調が長引くことも。
6月の薬膳的セルフケア
湿を追い出す生活習慣
- 軽く汗をかくようなウォーキングや半身浴
- 部屋の換気・除湿で環境から湿を減らす
- 冷たいもの・甘いもの・脂っこいものは控えめに
脾をいたわる食事習慣
- よく噛んでゆっくり食べる
- 温かく消化の良いスープやおかゆ中心に
- 胃腸を整える香りのある食材を取り入れる
6月におすすめの食材と理由
この時期は、体の余分な水分を出すこと、胃腸を元気にすること、気分をスッキリさせることが大切。
それにぴったりな食材を紹介します。
余分な水分を出す食材
- はと麦:むくみや肌荒れに。スープやごはんに混ぜて
- 冬瓜:体の熱と湿をスッキリさせる。さっぱり煮物に
- 黒豆:水分バランスを整えながら栄養も補える
- きゅうり:火照りやのどの渇きに。水分補給にも
胃腸を助ける食材
- 山芋:消化にやさしく、疲れた胃腸をいたわる
- とうもろこし・大豆:栄養があって消化にもよい
- なつめ:疲れやすい・寝つきが悪い時のサポートに
気分をスッキリさせる食材
- 陳皮(ちんぴ):みかんの皮を干したもの。香りでお腹も気持ちもスッキリ
- しそ・みょうが・ミント:爽やかな香りで気分転換に◎
- レモン・ライム:さっぱりとした酸味でリフレッシュ!
苦味がちょっと役立つ食材
- ゴーヤ:胃をシャキッとさせて、夏に向けた体づくりに
- セロリ・レタス:イライラしがちな時に、気持ちを整えてくれる
まとめ:梅雨のモヤモヤは、体と気持ちを整えるチャンス
6月は体の中にも湿気がたまりやすく、不調が出やすい季節。
でも、少しだけ「食べるもの」や「過ごし方」を意識するだけで、心も体もグンとラクになります。
雨の日も、薬膳のやさしい知恵で自分をととのえる時間を楽しんでみてくださいね^^
あわせて読みたい


【5月】気持ちがふさぎやすい季節。「気滞」と「湿気」に備える薬膳養生
新緑がまぶしく、気持ちのよい季節。それなのに、5月は意外と不調を感じる人が多い時期でもあります。 連休明けの疲れ、生活リズムの変化、初夏に向かう気候のゆらぎ。...
あわせて読みたい


【7月】夏バテ・イライラ・寝苦しさに。心と体をクールダウンする薬膳的ケア
本格的な夏が始まる7月。気温が高くなり、汗をかく量も増える時期ですね。 「なんだか疲れやすい」「寝つきが悪い」「イライラする」「体が熱っぽい」 …そんな不調を感...